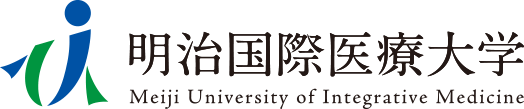修士課程(通信制)
通信教育課程
働きながら鍼灸を奥深くまで学び、
スペシャリストさらには指導者を目指す!
修業年限
標準修業年限は2年です。
また、長期履修学生制度を利用することで修業年限を3年とする履修コース(3年制コース) または4年とする履修コース(4年制コース)を選択することができます。
専攻分野・研究内容
専攻分野は、伝統鍼灸学、鍼灸基礎医学、鍼灸臨床医学、健康予防鍼灸学 の4つに区分します。
伝統鍼灸学分野
医学古典や東洋医学の理論、経絡経穴学、四診法、伝統鍼灸学の治療法などに関する専門的な知識を学修するとともにそれらに関する研究を行う分野です。東洋医学の基礎、伝統鍼灸学などに関する特論(講義)、演習、研究法を学修し、特別研究において上記の研究課題を追求します。
鍼灸基礎医学分野
形態学、機能学、免疫学、薬理学に関する専門的な知識を学修するとともに鍼灸刺激の生体反応とその機序解明に関わる研究を行う分野です。形態学、機能学、免疫・生化学、薬理学、基礎鍼灸学(鍼灸理論や鍼灸技術)の特論(講義)、演習、研究法を学修し、特別研究において鍼灸刺激の生体反応およびそれらの作用機序などを追求します。
鍼灸臨床医学分野
鍼灸臨床と深く関わる疾患や症候に関する専門的な知識を学修するとともにそれらに対する鍼灸治療の臨床効果とその機序解明に関する研究を行う分野です。内科学、整形外科学、外科学、脳神経外科学、麻酔科学、泌尿器科学、内科系臨床鍼灸学、整形外科系臨床鍼灸学、外科系臨床鍼灸学の特論(講義)、演習、研究法を学修し、特別研究において上記の研究課題を追求します。
健康予防鍼灸学分野
スポーツ鍼灸、予防・未病医学、美容鍼灸、産業鍼灸・高齢鍼灸などの鍼灸医学の応用領域に関する専門的な知識を学修するとともにそれらの領域における鍼灸の有効性に関する研究を行う分野です。健康鍼灸学、スポーツ鍼灸学、加齢鍼灸学の特論(講義)、演習、研究法を学修し、特別研究において上記の研究課題を追求します。
学位・資格
修士(鍼灸学)の学位を授与します。本研究科を修了した者は、はり師・きゅう師の学校(養成施設)における専門基礎分野および専門分野に関する科目の教員資格が認められています。ただし、教授できる授業科目については、原則として専攻した分野に関連する領域となります。

ビデオ教材を用いたオンライン学修システム
通信制の講義は全てインターネットを用いたビデオ配信形式で実施します。
ビデオ講義はいつでもどこでも何度でも繰り返し視聴できるので、自分のペースで学修を進めることができます。
長期履修学生制度

通常2年制で学ぶ履修内容を3年若しくは4年に分割して履修できます。
延長に伴う授業料の増加はありませんので、就業中の業務時間と学修時間などを検討の上ご判断下さい。

スクーリング制度
研究に必要な実務や技術、操作方法などを学ぶ研究方法論に関する内容はビデオや印刷教材等による授業だけでは限界があることから、面接授業による丁寧な解説・指導でより効果的な学修を行います。大学の付属施設(キャンパス内に設置する附属病院、附属鍼灸センター若しくは校舎内の研究室)において、原則として月に1回、1日大学で学習する程度の頻度になります。
よくある質問 Q & A
- どんな授業内容ですか?
- 統合医療をはじめ基礎・臨床鍼灸医学を学ぶ基盤科目の他、専攻分野毎の専門科目や研究方法論を学んで頂きます。学修方法はオンラインのビデオ配信を利用した講義の視聴と小テストとレポート課題です。また、スクーリングによる直接指導もあります。
- 何回大学へ行くことになりますか?
- 原則は、【月1回週末の土日を本学への通学する】を年8回実施します。具体的な時期や日数などは指導教官と相談の上、調整します。
- 途中で履修期間を延長できますか?
- 履修期間は、変更申請・許可によって延長又は短縮することができます。但し、在学中に履修期間の変更が認められるのは、1回限りです。
- 遠距離からのスクーリングに対する措置などありますか?
- 通信教育課程の学生にはJRの学割が適応されます。また宿泊場所は近隣の宿泊施設をご利用ください。
- 博士課程への進級はできますか?
- 本学大学院通信教育課程を修了し、修士号を取得すれば、博士課程への進学が可能になります。
特別研究テーマ・修了生研究報告テーマ
特別研究テーマ
| 分野 | 研究指導ユニット | 特別研究テーマ |
|---|---|---|
| 伝統鍼灸学 | 鍼灸医学系 | (1)東洋医学の基礎理論、診察・治療、養生に関する研究 (2)経絡・経穴に関する基礎的、臨床的研究 (3)日本の伝統鍼灸に関する調査研究 |
| 鍼灸基礎医学 | 現代医学系 | 解剖学 (1)鍼灸刺激による皮膚組織の形態学的変化の研究 (2)皮膚感覚受容器の機能形態学的研究 (3)皮膚感覚と運動感覚の連関理解のための機能形態学的研究 |
| 生理学 (1)鍼灸刺激による機能的変化、特に循環、呼吸、代謝などの植物性機能の変化に関する研究 |
||
| 免疫・微生物 (1)免疫学と鍼灸臨床に関する研究 |
||
| 鍼灸医学系 | 鍼灸基礎医学 フィジカル ・治効機序に関する基礎的研究 ブレインメンタル ・メンタルと脳機能に関する基礎的研究 ソーシャル ・社会要因に関する基礎的研究(アンケート調査や教育に関する分野) |
|
| 鍼灸臨床医学 | 現代医学系 | 内科学 (1)呼吸器疾患の臨床的研究 |
| 外科学 (1)外科系疾患の臨床的研究 |
||
| 整形外科学 (1)運動器系の臨床的研究 |
||
| 鍼灸医学系 | フィジカル ・各疾患(運動器系・内科系・外科系など)に関する基礎的・臨床的研究 ブレインメンタル ・メンタルヘルス(うつやストレス疾患など)に関する基礎的・臨床的研究 ソーシャル ・社会的要因が関連する疾患(慢性疾患・緩和医療など)に関する基礎的・臨床的研究 |
|
| 健康予防 鍼灸学 |
鍼灸医学系 | フィジカル ・運動機能(スポーツやコンディショニング、ロコモティブシンドロームなど)に関する予防的研究(基礎・臨床) ブレインメンタル ・脳機能(疲労・不眠・美容など)に関する予防的研究(基礎・臨床) ソーシャル ・社会的要因が関連する疾患に関する予防的研究 |
※特別研究テーマについては、変更となる場合があります。
修了生研究報告テーマ
| ◆2021年度修了生 |
|---|
| 高齢者の慢性疼痛患者に対する運動療法の文献的考察 |
| 鍼灸師の灸施術に関する意識調査 -北海道の鍼灸師の透熱灸に関する意識調査- |
| 顔面部と遠隔部の鍼刺激における美容効果の比較 |
| 経穴刺激が実験的に作成した筋肉痛に及ぼす影響(探索的検討) |
| さいたま市の開業鍼灸院・鍼灸整骨院等において勤務する鍼灸師の鍼灸補助行為併用に関するアンケート調査(予備調査) 〜補助行為の実態と今後の課題について〜 |
| くるみ灸が自律神経に与える影響 |
| 鍼灸専門学校教育におけるリメディアル教育の再考 -全国の教員・学生調査から- |
| 鍼灸関連の国内学会誌における経穴の掲載頻度に関する研究 |
| あはき教育におけるICTの活用に対する態度と活用実態に関する教員調査 |
| 顔面部への鍼刺激が顔循環動態に及ぼす影響について -金鍼とステンレス鍼の違いについて- |
| エコーガイド下での刺鍼に関する臨床的有用性の文献的研究 |
| コロナ禍前後における学生意識の変化について |
| 脳機能MRIを用いた内関刺激による脳活動変化の研究 |
| 低周波鍼通電刺激が等尺性膝伸展最大筋力に及ぼす影響 |
| 月経痛に対するセルフケア灸の有用性を検討するためのプロトコール研究 |
| ◆2020年度修了生 |
| トリガーポイント鍼治療とトリガーポイント注射の有用性に関する文献的研究 |
| パラパワーリフティング選手のコンディション調査 ―POMSおよび東洋医学的体質問診票を用いた検討― |
| 鍼灸治療の骨盤位変換の有効性についての文献的検討 ―鍼灸治療骨盤位変換効果に関する論文のメタアナリシス― |
| 鍼灸院に来院する高齢者のフレイルの状況 |
| シリコン素材の円皮鍼による刺激が重量感覚に及ぼす影響 |
| 高齢者の日常生活の満足度と運動能力の関係についてのコホート研究 ―介護予防体操の活動が非常生活の質に及ぼす影響― |
| 『扁鵲神応針灸玉龍経』における「玉龍歌」の臨床的内容と文献学的研究 |
| 硬結と鍼灸に関する文献調査―硬結の定義、研究、鍼灸臨床における現状と課題― |
| 原発性月経困難症に対するツボ療法の有効性に関する文献的調査 |
| 再生医学における鍼灸に関する文献調査 |
| 皮膚電気抵抗(ノイロメトリー)と自律神経活動評価との関連性の検討 ~運動負荷時の心拍変動・唾液アミラーゼ活性を指標とした検討~ |
| 顔面部への毫鍼術と鍉鍼術の美容効果の比較 ―皮膚色、皮膚表面温度、皮膚粘弾性を用いた検討― |
| 慢性痛を有する女子アスリートの心理的、身体的特徴 |
| はり師・きゅう師養成施設における東洋医学臨床論に関する教育現状の調査 |
| ローラー鍼刺激による筋硬度変化の検討 ―筋緊張部と非緊張部の刺激による比較― |
| 澤田流鍼灸「裏四霊」の取穴位置についての考察 ―澤田流鍼灸の遺産を現代鍼灸で活用するために― |
| 冷えに対する鍼灸治療―文献調査からみる現状と課題― |